記者であるわたくしは沖縄に移住して10年になりました。本土から来た私が驚いたり、思わず笑ってしまったりした「沖縄あるある」をご紹介します。本土にはない、沖縄で当たり前の「あるある」を事前に知っていれば、沖縄の楽しみ方が全然変わってきます。これから沖縄旅行や移住を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
日常生活の沖縄あるある
沖縄での暮らしには、本土とは異なる独自の感覚や習慣が根付いています。日々の生活の中で「沖縄らしさ」を感じる場面に数多く出会います。
「ウチナータイム」でのんびり
沖縄では「ウチナータイム」と呼ばれる独特の時間感覚があります。約束の時間に少し遅れても気にしない、「だいたい」の感覚で物事が進むことが多いです。最初はイライラするかもしれませんが、この「なんくるないさ」(何とかなるさ)の精神に触れると、心がほぐれていきます。
一年目は暖かいけど、二年目からは「寒い」と感じる
移住一年目は「冬でも暖かい!」と喜んでいたのに、二年目からは「寒い…」と感じるようになるひとが多いです。体が亜熱帯気候に順応して、わずかな気温変化にも敏感になるようです。冬場の20℃が寒く感じるようになるのは沖縄あるあるです。
ウチナーンチュは海で泳がない
地元の人は海で泳がない人が多いです。日焼け対策もあると思いますが、洋服を着て泳ぐことが多いです。ウチナーンチュにとって海は「ビーチパーティー」を楽しむ場所です。水着で泳いでる人を見たら、ほぼ観光客か本土から移住してきた人でしょう。
雨が降っても傘をささない
ウチナーンチュはちょっとした雨なら傘をささない人が多いです。小雨でなくても傘をささない人もいます。小中学生は、土砂降りでも傘を差さずにずぶ濡れのまま歩いたりするので、思わず車で送ってあげようかと言ってあげたくなります。
台風の日の過ごし方
沖縄地方へ台風が近づくことが多いため、暴風域が当たり前の沖縄では動じない方が多いです。「まだ強風域なんだね〜」などと外の様子を見て風が弱まってる合間をみて、映画館に行ったり、ここぞとばかりに動き出す人もいます。台風をよく知っているからこその行動ですね。
ヤモリは大切な「同居人」
家の中にヤモリがいても大抵のウチナーンチュは驚きません。むしろゴキブリを食べてくれる味方として歓迎されているようです。「家守(やもり)」の名前の通り、家を守ってくれる存在なのです。
食文化の沖縄あるある

沖縄の食文化は、本土出身者にとって新鮮です。食材の種類や調理法だけでなく、日常で使う言葉やスーパーの呼び方にも、地域の個性が表れています。
「そば」といえば沖縄そば
沖縄そばは蕎麦粉ではなく小麦粉で作られています。スープは豚骨と鰹節ベースの醤油味で、三枚肉(豚の角煮)や軟骨ソーキが乗っています。そして年越しそばは沖縄そばです。焼きそばも本土で食べる焼きそば麺ではなく、沖縄そばの麺を使っています。
「サンエーに行く」はスーパーに行くという意味
沖縄では「スーパーマーケット」を「サンエー」「ユニオン」などの店名で呼ぶ傾向があります。私の経験では「サンエーに行ってくる」というのは「スーパーに行ってくる」という意味です。最初は戸惑いますが、すぐに使うようになるあるあるです。
私が教える交通事情の沖縄あるある
沖縄では車が欠かせない移動手段ですが、運転していると独特の交通事情に驚かされることがあります。車の種類や道路の特徴、そして渋滞の多さなど、知っておくと安心できるでしょう。
よく見かけるナンバープレート!「Y」「れ」「わ」の謎
沖縄では特徴的なナンバープレートを見かけます。「Y」ナンバーは米軍関係者の車、「れ」「わ」ナンバーは観光客か、一時的にレンタルしてる米軍関係者の車がほとんどです。運転に慣れていない場合が多いので、近くにいたら警戒する人が多いです。
道路が超滑る!
沖縄の道路は滑りやすいです。これは潮風の影響で結晶化した塩分が路面に付着していたり、アスファルトの成分に珊瑚礁の琉球石灰岩を使用しているため、路面が濡れると滑りやすいそうです。運転するとき(特に雨天時)は注意してくださいね。
渋滞はいつものこと
沖縄は車社会です。大きな国道・県道に限った話ではありませんが、特に那覇や名護近くの渋滞は日常茶飯事です。
地元の人は裏道を知っていたり、渋滞を避ける時間帯に移動したりするなど工夫をしています。時間に余裕を持って行動しましょう。
ウチナーンチュの気質あるある

沖縄の人々と接していると、その温かさや助け合いの精神、そして芯の強さに驚かされます。言葉や行動に、人と人とのつながりを大切にする文化が息づいているのを感じます。
「我慢強い」はウチナーンチュの代名詞
ウチナーンチュは我慢強いと言われています。戦後の苦難を乗り越えてきた歴史が今の県民性に影響しているのかもしれません。困難な状況でも前向きに考え、黙々と頑張る姿勢や辛抱強い場面をみると、私なら文句を言ってしまうなといつも感心させられます。
「ゆいまーる」の精神で助け合う
「ゆいまーる」と呼ばれる相互扶助の精神が今も生きています。地域の行事や冠婚葬祭では、近所の人々が自然と助け合う光景が見られます。困っている人がいれば手を差し伸べるのが当たり前という文化に、人の温かさを感じます。
「イチャリバチョーデー」で絆を大切に
「イチャリバチョーデー」(会えば兄弟)という言葉があるように、縁あって出会った人との絆を大切にする文化があります。知らない人には最初はやや警戒心を持つこともありますが、いったん打ち解けると非常に親身になってくれる人が多いのが沖縄人の魅力です。
年配者は意外と英語が上手い
私の経験上、年配のウチナーンチュは英語を話せる方が多いです。アメリカ統治時代の影響で、子供時代にアメリカ人との交流が多く、自然と英語が身に付いたのでしょう。とてもきれいな発音の流暢な英語で、外国人と話し始める方を見て驚くこともよくあります。
行事・風習の沖縄あるある
伝統や先祖を大切にする沖縄では、今も旧暦に沿った行事や神聖な場所への信仰が受け継がれています。地域ごとに特色があり、文化や歴史に触れるたびにその奥深さを感じます。
旧暦が今も現役、お盆は旧暦
沖縄ではまだ旧暦が現役で使われています。特にお盆などの伝統行事は旧暦で行われることが多いです。本土のお盆が8月中旬なのに対し、沖縄では旧暦の7月に行われます。そのため、毎年日付が異なり、9月頃になることもあります。
沖縄のお墓は大きい
初めて沖縄のお墓を見た方は「えっ?」と驚くでしょう。沖縄のお墓は巨大な造りになっています。4〜5月にご先祖様をしのぶ伝統行事「清明祭(シーミー)」という行事があり、親族が集まってお墓の前でお祝いをします。ピクニックのように見えてもとても大切な行事なのです。
エイサーの迫力に驚く
エイサーは旧盆の時期に行われる伝統的な踊りで、太鼓のリズミカルな音と躍動感ある踊りが特徴です。観光用のショーとしてだけでなく、各地域で伝統が守られており、若者たちが熱心に練習する姿も見られます。一度見るとその迫力に圧倒されることでしょう。
御嶽(うたき)は神聖な場所
沖縄には御嶽(うたき)と呼ばれる聖地や拝所が各地にあります。これらは琉球時代からの信仰の場所で、今でも地域の人々によって大切に守られています。聖地を訪れる際は静かに振る舞い写真撮影を控えるなど、地元の信仰を尊重しましょう。
沖縄移住・旅行者が知っておくと便利なこと
沖縄での暮らしや旅をもっと楽しむためには、少しだけ方言を覚えておくと良いでしょう。あたたかな交流が生まれやすくなります。
沖縄らしさ満点のよく使う方言フレーズ
沖縄の方言を少し覚えると地元の人との距離がぐっと縮まるでしょう。日常会話でよく使われるフレーズをご紹介します。
- 「はいさい」(男性)「はいたい」(女性):「 こんにちは」
- 「しに」「でーじ」 :とても(しに・でーじ◯◯=( とても◯◯だよ)
- 「~だからよ・~だからさ」 : ~だよね(「~だからよ」=そうだねー)
- 「~やっさ」 : ~だよ、~だぞ(「これが沖縄そばやっさ」=これが沖縄そばだよ)
- 「あきさみよー」 : あらまあ!うわー!(驚きや軽い落胆を表す感嘆詞)
- 「じょうとう」 : 良い、素晴らしい、OK(「これは上等さー」=これは良いものだよ
まとめ

沖縄の日常には、本土では考えられないような驚きや発見がたくさん詰まっています。この記事で紹介した「あるある」はほんの一部です。実際に訪れて、地元の人と触れ合うことで、もっと知ることができるでしょう。
「なんくるないさ」の精神で、ぜひ「沖縄の懐」に飛び込んでみてください。温かい人の輪と、のんびりとした時間が、きっとあなたの心を癒してくれるはずです。沖縄の文化を尊重しながら、あなただけの「沖縄あるある」を見つける旅に出かけましょう。
筆者あとがき
沖縄に移住して10年が過ぎようとしています。今では「ここが私の居場所だ」と心から思えます。最初に目に飛び込んでくる青い海と空の美しさは格別ですが、本当の魅力は沖縄の人々の優しさでしょう。
困ったときに黙って手を差し伸べてくれる温かさ、「イチャリバチョーデー」の精神に何度も救われてきました。ウチナータイムの流れる時間の中でこころが癒されるのを感じます。
もちろん、移住には車の必要性や塩害対策、台風への備えなど、現実的なこともあります。でも、それ以上に得られるものは大きく、沖縄の文化や歴史を尊重し、この地で幸せに暮らせることに感謝しながら毎日を過ごしています。
美しい海だけでなく、人々の暮らしや伝統に触れてこそ、本当の沖縄の魅力が見えてきます。ぜひあなたも「なんくるないさ」の心で、「沖縄の懐」に飛び込んでみませんか?


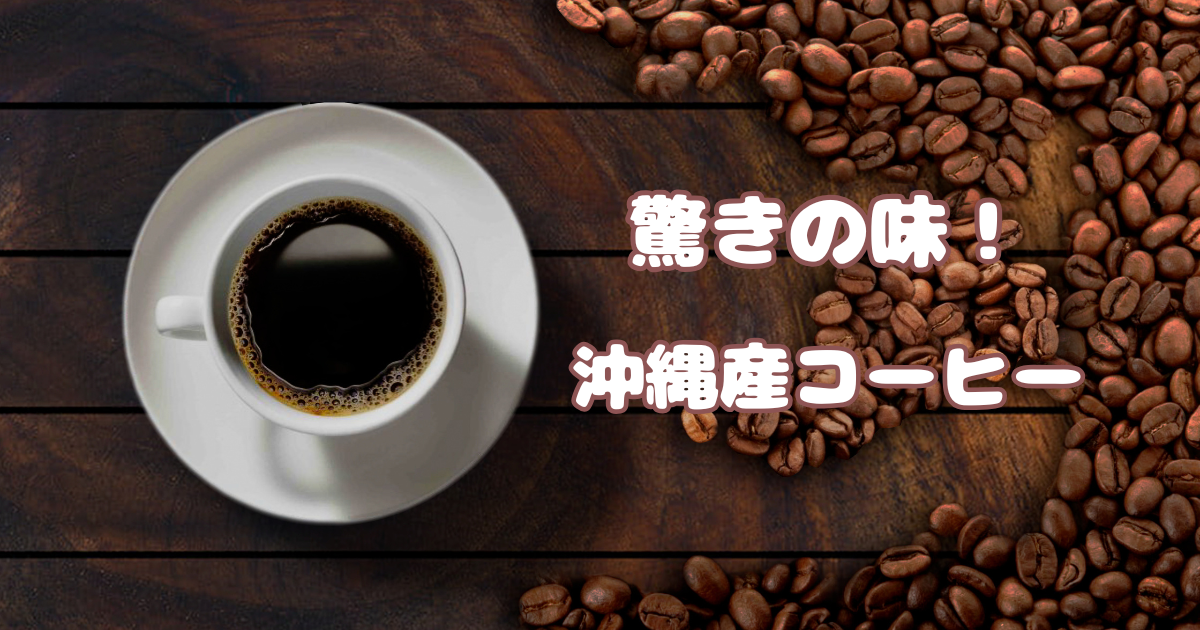
コメント