今からおよそ900年前の平安時代末期、ちょうど平家物語に記される頃の時代、一人の武将がその名を轟かせていました。その男の名は源為朝(みなもとのためとも)。並外れた弓の腕と怪力で、鬼神の如き強さを誇り、鎮西八郎(ちんぜいはちろう)の異名を持つ猛将です。そんな為朝が、まさか当時の沖縄に足跡を残していたとは、驚きですよね!さあ、英雄・為朝の伝説を求めて、沖縄を巡る旅に出かけましょう。
第一章:鬼神の如き武勇!鎮西八郎・源為朝とは何者だったのか
源為朝、通称鎮西八郎。この名前を聞いただけで武勇に長けた豪傑の姿が目に浮かぶ方もいるのではないでしょうか。彼は平安時代末期に活躍した武将で、源氏の一族に生まれました。その武勇は当時からすでに伝説的なものでした。
彼の最も有名な逸話といえば、やはりその驚異的な弓の腕でしょう。成人男性が5人がかりでやっと引けるような強弓を軽々と引き絞り、その矢は鎧を貫き、時には一矢で二人の鎧武者をまとめて射抜いたと言われています。
あまりにも勇猛すぎる為朝に手を焼いた父・源為義は、為朝が13歳の頃、彼を九州へ追放してしまいます。しかし為朝は追放先の九州(鎮西とも呼ばれます)を舞台に暴れまわり、各地の豪族たちとの戦いにことごとく勝利します。
そしてわずか3年後、僅か十代のうちに九州一帯を制圧するに至りました。彼の異名である鎮西八郎はその武勇伝に由来するものです。
このような武勇伝は、史実として語り継がれるだけでなく、後世の物語や伝承にも色濃く反映されています。九州地方を舞台にした彼の活躍は、多くの人々の間で語り草となり、その武名は日本全国に広まりました。
その強さゆえに、為朝は恐れられ、同時に人々の心を惹きつける魅力的な英雄として、語り継がれてきたのです。まさか、そんな伝説の武将が、遠く離れた沖縄の地に足跡を残していたとは、なんともロマン溢れる話ではありませんか!
第二章:伝説の始まりの地へ~荒波を越えて辿り着いた運天

保元の乱で父と共に敗れた源為朝は、伊豆大島へと島流しとなります。しかし、沖縄に残る伝説によれば、彼はそこで終わるような男ではありませんでした。
屈強な肉体と不屈の精神を持つ為朝は、流された島で力を蓄え、再び歴史の表舞台へと戻ろうとします。そして、彼の次なる舞台となったのが、遥か南の島、沖縄本島だったのです。
どのようにして伊豆大島から沖縄へと辿り着いたのか、その経緯は定かではありません。一説には、嵐に巻き込まれて船が難破し、「運を天に任せる」境地に至った後、偶然にも沖縄北部の港に漂着したと言われています。
その伝承に因んで、彼の漂着地一帯は運天という地名で呼ばれ、現在に至ります。運天港は、沖縄本島の北部、現在でいうと国頭郡今帰仁村(くにがみぐん なきじんそん)に位置しています。
天然の良港として知られる運天は当時おそらく、豊かな自然に囲まれた静かな漁村だったことでしょう。そこに、屈強な体格をした武士が現れたのですから、地元の人々はさぞ驚いたのではないでしょうか。
為朝は、その強さと異様な風貌から、すぐに人々の間で特別な存在として認識されたと考えられます。現在の運天港周辺は、美しい海に囲まれた景勝地として有名です。
近くには、運天森(うんてんむい)と呼ばれる小高い丘があり、現在は運天森園地という名称で公園化されています。園内に設置されている展望台は、運天港や周囲の島々を一望できる絶景スポットです。
為朝が最初に見た沖縄の風景も、きっとこのような雄大なものだったのではないでしょうか。伝説の始まりの地・運天を訪れれば、遥か昔の英雄の息吹を感じることができるかもしれません。
第三章:琉球の女性との出会い~為朝が妻を娶った大里グスクの謎
運天に漂着した為朝は、やがて一人の美しい女性と出会い、深く愛し合うようになったと伝えられています。伝説によると、彼女は大里按司(おおざとあじ)という豪族の娘であり、その実家こそが大里グスク(おおざとぐすく)だったと言われています。
しかし、この大里グスク、実は沖縄本島内に二つ存在すると考えられているんです。
一つは、現在、南城市(なんじょうし)にその跡が残る島添(しましー)大里グスクです。こちらは、琉球王国の成立以前、按司と呼ばれる地方の豪族が割拠していた時代に栄えたグスクの一つです。
自然の地形を活かした堅牢な石垣が特徴で、眼下には広大な田園風景が広がっています。伝説によれば、為朝はこの南城市の大里グスクを拠点に、周辺地域を治めていたとも言われています。
現在の南城市大里周辺は、のどかな田園地帯が広がり、歴史を感じさせる史跡も点在しています。近くには、琉球開闢(かいびゃく)の祖とされるアマミキヨが降り立った聖地斎場御嶽(せーふぁうたき)など、沖縄の神聖な場所も存在します。
そして、もう一つが、糸満市(いとまんし)にかつて存在した島尻(しまじり)大里グスク)で、為朝の妻の実家はこちらだったという説が有力です。
糸満市は、古くから漁業が盛んな地域で、独特の文化が育まれてきました。島尻大里グスクがあった糸満市大里周辺は現在、住宅地や畑が広がっており、当時の面影を探すのは難しいかもしれません。
為朝が娶った女性の実家が南城市の大里グスクだったのか、それとも糸満市の島尻大里グスクだったのか。どちらが真実かは、今となっては謎に包まれています。
しかし、どちらの地にも、為朝と琉球の女性との間に育まれたであろう、甘く切ないロマンチックな物語が息づいているように感じられます。
第四章:妻子との別れと新たな旅立ち~牧港に残る悲恋の伝説

愛する妻と可愛い子供たちを得て、沖縄での生活を送っていた為朝ですが、その平穏な日々は長くは続きませんでした。再び故郷を思い、あるいは新たな野望を抱いたのかもしれません。
為朝は、妻子を残して沖縄を離れることを決意します。そして、彼が沖縄を後にしたとされる場所が、現在の浦添市(うらそえし)にある牧港(まきみなと)なのです。
牧港川の河口に位置していた港、当時沖縄本島内の港の中でも規模が大きな港だったようです。為朝はそこから一隻の船に乗り込み、再び荒波の海へと旅立って行ったと言われています。
妻子との別れのシーンは、想像するだけで胸が締め付けられるような気持ちになります。異国の地で築き上げた温かい家庭、愛する妻と幼い子供たちを残して旅立つ為朝の心中はいかばかりだったでしょうか。
残された妻子の悲しみも、計り知れないものだったでしょう。一説では、為朝の妻子は幾度もこの地を訪れ、為朝の帰還を待ちわびていたそうです。それを意味する待つ港から転じて牧港という地名となったとも言われています。
現在の浦添市牧港周辺は、住宅地が広がり、商業施設なども立ち並ぶ賑やかな場所となっています。牧港川を遡るように東へ向かうと琉球王国の王陵である浦添ようどれがあり、湾岸道路沿いに南の那覇方面へ進めば大型ショッピングモールパルコシティに至ります。
為朝が旅立ったであろう牧港の地を訪れ、遥か昔の悲恋の物語に思いを馳せてみるのも感慨深い体験となるでしょう。なぜ為朝は妻子を残して沖縄を離れたのか、そしてその後彼はどこへ向かったのか。多くの謎が残るこの伝説は私たちの想像力を掻き立て、歴史のロマンへと誘います。
第五章:沖縄各地に残る為朝伝説、その真偽は?
鬼神の如き武勇を誇った為朝が、保元の乱に敗れた後、遠い琉球の地に辿り着き、愛する妻子をもうけた後、またいずこかへと旅立っていった。そんな物語にまつわる伝承が沖縄の各地に残されています。
しかしその物語は、史実として残されている定説とはかなり異なります。歴史で語られる為朝は戦に敗れて伊豆大島へと島流しになった後、その地で生涯を終えたとされています。
為朝伝説は史実と物語が入り混じり、まことしやかな部分も多く残されています。しかし、そのロマンあふれる物語は、時代を超えて語り継がれ、沖縄の歴史と文化に深く根付いていると言えるでしょう。
まとめ

今回は、平安時代末期の最強武将と謳われた源為朝こと「鎮西八郎」が沖縄に残したとされるゆかりの地をご紹介しました。
この伝説に触れることで、私たちはいにしえの英雄の息吹を感じ、遥かなる琉球の歴史に思いを馳せることができるのです。皆さんもぜひ、為朝伝説の足跡を辿る旅に出かけてみませんか?新たな発見と感動がきっとあなたを待っているはずです。
あとがき
牧港を出航し沖縄を後にした為朝が、再び沖縄に帰ってくることはありませんでした。その後の彼がどうなったのか、その足跡は知られていません。そして彼が沖縄の地に残した男の子がその後、沖縄に新たな時代をもたらす英傑へと成長することになるのですがその話はまた別の機会に。


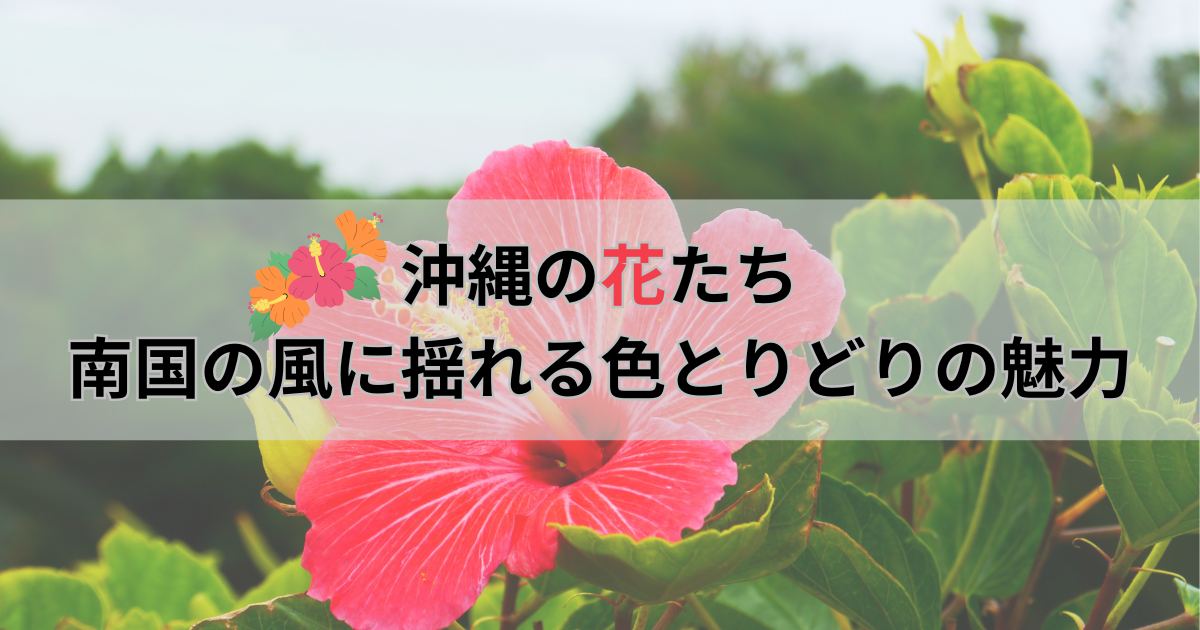
コメント