第二次世界大戦の激戦地となった沖縄。その戦禍で失われたとされていた琉球王国の歴代国王の肖像画「御後絵(おごえ)」が、79年の時を経て、アメリカから故郷へ戻ってきました。これまで白黒写真でしかその姿を知ることができなかった幻の文化財の鮮やかな色彩が、初めて明らかになり、多くの人々に感動を与えています。一体、この国宝級の宝はどのようにして海を渡り、なぜ今、返還が実現したのでしょうか。本記事では、その奇跡的な物語を紐解いていきます。
御後絵とは?琉球王国の歴史と文化を伝える至宝
琉球王国の豊かな歴史と独特の文化を現代に伝える、最も貴重な文化財の一つに「御後絵(おごえ)」があります。
これは、歴代の琉球国王が亡くなった後に、王の功績を称え、その姿を偲ぶために描かれた肖像画です。
御後絵は単なる絵画ではなく、琉球王府に仕えた最高の絵師たちが、当時の技術の粋を集めて制作した芸術品であり、王国の威厳を象徴するものでした。
絵画の中心には、儀式で身につける豪華絢爛な衣装をまとった国王の姿が、ひときわ大きく描かれています。
その周囲に家臣が控えめに配置される構図は、国王の絶対的な権威と威光を強調しているのかもしれません。
これらの絵は、琉球王国の権威と美術の粋を象徴するものであり、歴史的にも美術的にも非常に高い価値があるとされています。
このようにして描かれた御後絵は、歴史的な資料としての価値はもちろんのこと、美術品としても比類ない高い評価を受けています。
これらの御後絵は、かつておよそ20点存在していたとされています。しかし、1945年の沖縄戦で、旧王家である尚家の邸宅「中城御殿(なかぐすくうどぅん)」が戦火に遭い、焼失しました。
その結果、すべての御後絵が失われてしまったと考えられていました。戦後、わずかに残されたのは、戦前に撮影された一部の白黒写真のみでした。
このため、御後絵がもともと持っていた鮮やかな色彩や細かな筆致は、長年にわたり謎に包まれたままでした。
今回、79年という長い歳月を経て、幻の文化財の一部が奇跡的に発見され、その鮮烈な色彩が初めて明らかになったのです。
この出来事は、失われた歴史の空白を埋める感動的な出来事として、沖縄の人々に大きな希望をもたらしました。
奇跡の発見、アメリカの住宅で見つかった経緯

2023年1月、FBIボストン支局のジェフリー・J・ケリー特別捜査官は、ある通報を受けました。
それは、第二次世界大戦に従軍していた退役軍人の住宅から、略奪された文化財かもしれない大量のアジア美術品が見つかったというものです。
元軍人の死去後、遺品を整理していた家族が、屋根裏部屋で美術品を発見し、通報に至ったとされています。
鑑定にあたった専門家は、肖像画の様式や絵の具、そして巻物に記された文字などから、これが間違いなく琉球王国の文化財であると特定します。
その後、FBIは盗難美術品に関するデータベース「全米盗難美術品ファイル」で照合し、スミソニアン博物館に調査を依頼しました。
その結果これらの美術品は、琉球王朝の第13代国王尚敬と第18代国王尚育の「御後絵」を含む18〜19世紀の絵巻物6点、19世紀の手書きの沖縄地図、そして陶器や陶磁器の破片であることが判明しました。
長年の謎に包まれていた御後絵が、アメリカの一般家庭で発見されたことは、歴史研究者や沖縄の人々にとって、まさに奇跡と呼べる出来事でした。
持ち出しの真相に迫る〜真栄平房敬さんの証言〜
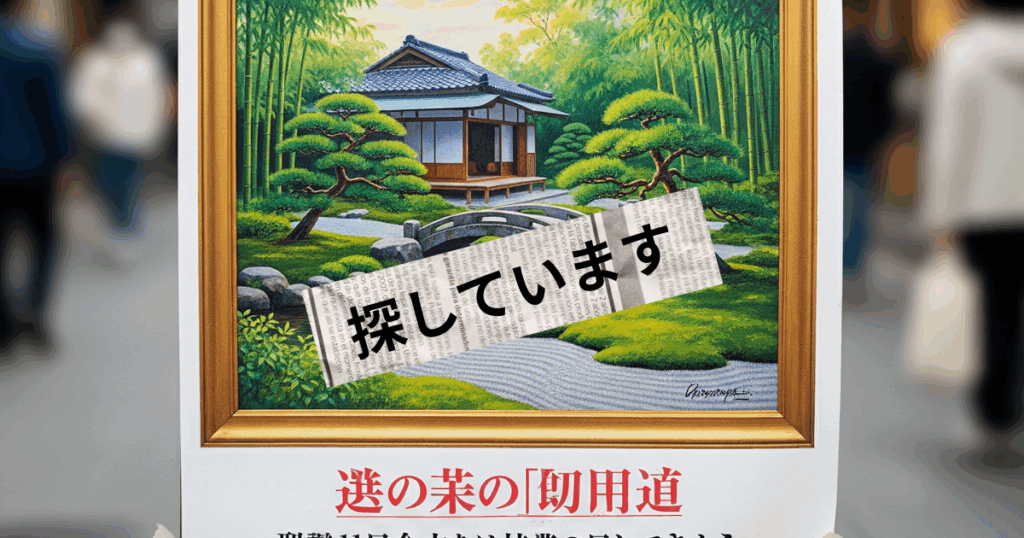
御後絵がいつ、誰によって、どのようにして沖縄から持ち出されたのかは、長らく謎に包まれていました。
しかし、その背景には、沖縄戦の混乱の中で文化財を守ろうとした人々の存在と、長年にわたる真摯な捜索がありました。
戦前、御後絵は旧王家の邸宅「中城御殿(なかぐすくうどぅん)」に保管されていましたが、戦火から逃れるために隠されました。
この時、宝物を隠す作業を手伝った一人に、元教員の真栄平房敬さん(2015年死去)がいました。
彼は、邸宅の宝物を別の場所に隠したと証言していますが、御後絵は終戦後も見つからず、その行方は分からなくなりました。
真栄平さんは「焼失したのではない。持ち去られ、どこかにあるはずだ」と信じ続け、捜索を諦めませんでした。
戦後8年が経った1953年には、屋敷の排水路に隠された「おもろさうし」などがアメリカで見つかり、沖縄に返還されたという吉報が届きます。
この出来事が、真栄平さんの確信をさらに強めました。彼は、宝物の種類や隠し場所などを詳細に記した「捜索願」をアメリカ側に送るなど、長年にわたり捜索活動を続けます。
80歳近くになった2000年には、真栄平さんは県の元学芸員である萩尾俊章さんと共にアメリカを訪問。
FBIやインターポールに協力を要請します。この訪米がきっかけとなり、御後絵を含む13点の文化財がFBIの「盗難美術品リスト」に登録されました。
しかし、これが実際に返還につながるかどうかは、まだ見えない状態でした。事態が急展開したのは、リスト登録から20年あまりが経った2023年のことです。
FBIに「盗難品リストに載っているものかもしれない」という通報が入り、捜査官がボストン近郊の住宅へ駆けつけます。
遺品とともに見つかった手紙には、「沖縄から持ち帰った」「尚男爵邸の廃墟で拾った」といった、沖縄戦での持ち出しを示唆する貴重な手がかりが記されていました。
この手紙と鑑定の結果、沖縄から持ち去られたものだと断定され、ついに返還が実現しました。
蘇る記憶、御後絵がもたらす感動と意義
79年という長い歳月を経て故郷へと戻ってきた御後絵は期間限定で、沖縄県立博物館・美術館で多くの人々の前にその姿を現していました。
人々が肖像画の前に立ち、これまで白黒写真でしか知ることのできなかった鮮やかな色彩を目の当たりにするとき、琉球王国の栄華な歴史と、沖縄戦で失われた文化への思いが、胸に迫ってくることでしょう。
御後絵は、単なる美術品ではなく、沖縄の人々にとって、失われた過去の記憶を呼び覚ます、かけがえのない存在となっています。
この御後絵の帰還は、沖縄戦の戦禍を生き延びた文化財が、まだ世界のどこかに残されているかもしれないという、大きな希望を沖縄社会にもたらしました。
この度の御後絵の発見と返還は、沖縄戦がもたらした文化的な悲劇と、文化財を保護することの重要性を改めて深く考えさせるきっかけとなりました。
御後絵は、戦争によって貴重な文化財が失われるという悲劇を静かに物語っています。
しかし同時に、人々が善意と熱意をもって協力すれば、一度失われたものでも再び取り戻せるという希望を象徴しているのです。
御後絵は、過去と現在を確かに繋ぎ、未来の世代に向けて、平和な社会と文化財を大切に守り継いでいくことのメッセージを力強く発信していると言えるでしょう。
まとめ

御後絵は、沖縄戦で失われた琉球王国の至宝です。 奇跡的に発見されたこの肖像画は、79年の時を経て故郷へと帰還しました。アメリカの一般家庭で見つかった御後絵は、日米の協力と人々の熱意によって返還が実現。
この出来事は、沖縄の歴史を伝えるだけでなく、平和と文化の大切さを訴えかける感動的な物語です。これからも、失われた文化財を探す活動は続けられていくでしょう。
あとがき
御後絵の物語をたどっていくと、心揺さぶられる感動があります。一人の沖縄の男性が抱き続けた「どこかにあるはずだ」という強い信念が、長い年月を経て、海の向こうで発見された文化財の帰還へと繋がったのですから。
今回の奇跡的な再会は、沖縄戦で失われた文化財が、今なおどこかに眠っているかもしれないという希望を私たちに与えてくれました。
その鮮やかな色彩を目の前にしたとき、琉球王国の歴史の重みと、文化を守り抜いた人々の思いを、肌で感じることができるのではないでしょうか。



コメント