沖縄の家や屋根の上でよく見かけるシーサーは単なる装飾品ではなく、古くから人々を守り続けてきた守り神です。本記事では、シーサーの奥深い歴史や知っておきたい豆知識、そして沖縄旅行でぜひ挑戦したいシーサー作り体験についてご紹介します。
守り神シーサーの起源と歴史
沖縄の守り神シーサーは、遥か遠い異国の地から長い時間をかけて沖縄にたどり着きました。そのルーツは紀元前まで遡る古代オリエント文明の獅子像にあると推測されています。
古代エジプトのスフィンクスに代表される獅子像は、王の権力や聖なるものの象徴として崇拝されていました。この獅子像がシルクロードを通り、中国へ伝わり「獅子」の形となります。(諸説あります。)
そして、13世紀から15世紀頃の琉球王国時代に、中国との交易を通じて沖縄へと伝来しました。
沖縄の方言で「獅子(しし)」が「シーサー」と発音されるようになり、守り神として人々の生活に溶け込んでいったのです。
シーサーが魔除けとして一般的に普及するきっかけとなったのが、日本に残存する中で最古にして最大とされる「富盛の石彫大獅子」にまつわる伝説です。
1689年、当時火事が頻発していた富盛(ともり)村の住民が、風水師の助言に従い、火災の原因とされる八重瀬岳の方角へ向けて獅子の像を設置したところ、火事が収まったと伝えられています。
これ以降、シーサーは火除けや災難を防ぐ守り神として村や家庭に置かれる習慣が広まりました。
「富盛の石彫大獅子」は、沖縄戦では激しい銃弾を受けながらも原形を保ち、村の歴史を見守り続けた奇跡の獅子としても知られ、現在では沖縄県の指定有形民俗文化財となっています。
このように、シーサーは単なる置物ではなく、沖縄の歴史と信仰、そして人々の願いが込められた文化遺産なのです。
シーサーの主な役割と込められた願い

沖縄の街を歩けば、家や建物の入り口で堂々とした姿で私たちを迎えてくれます。この守り神には、主に二つの大切な役割と、沖縄の人々の切実な願いが込められています。
一つは「魔除け」、もう一つは「福招き」です。
シーサーが家や村を見張るように設置されるのは、悪霊や災いが人の通る道から入ってくると考えられているからです。
その強面で邪気を追い払い、家や集落に災難が入ってくるのを防ぐ、これがシーサーの最も重要な魔除けとしての役割です。
特に、火災が頻繁に起こった歴史的背景から、火除けの守り神としても重んじられてきました。
大切なのは、「災いを防ぎ福を招く」というシーサーに込められた沖縄の人々の普遍的な願いを理解することでしょう。
設置場所と役割によるシーサーの3つの種類
シーサーは、設置された場所と果たす役割によって、大きく3つの種類に分類されます。それぞれの種類が、琉球王国の時代から現代に至るまで、沖縄の歴史と文化の中で独自の役割を担ってきました。
権威の象徴「宮獅子」
宮獅子(みやじし)は、かつての琉球王国時代に、王府に関わる場所や身分の高い人々の墓や寺院、城郭(じょうかく)などに置かれたシーサーです。
これらは魔除けというよりも、王府や支配階級の権威を示す象徴として作られた側面が強く、精巧な石彫で作られているのが特徴です。
沖縄にシーサーが伝わった初期の文化を伝える貴重な存在と言えます。
村全体を守る「村落獅子」
村落獅子(そんらくしし)は、その名の通り、集落や村全体を悪霊や災害から守るために設置されたシーサーです。
これらは対ではなく一体で置かれていることが多く、集落の鬼門や、火災の原因とされる山など特定の方向に向けて設置されています。
「富盛の石彫大獅子」のように、庶民の切実な願いから生まれた村落獅子が、王族中心だったシーサー信仰を民間へと広めるきっかけを作りました。
家庭の守り神「家獅子」
現代において最も一般的に見られるのが家獅子(いえしし)です。
これは、個人宅や一般家庭を守るために置かれるシーサーで、明治時代に庶民も瓦葺き屋根の使用が許されるようになってから普及しました。
屋根に置かれる屋根獅子は、瓦職人が余った瓦や漆喰でサービスとして作ったのが始まりとも言われ、その愛嬌のある姿は、沖縄の温かい文化を象徴しています。
シーサーの素材と現代における多様な姿

シーサーの姿や表情が一つとして同じものがないように、その素材や製作方法も多様です。伝統的な素材から生まれたシーサーは、沖縄の気候や文化を反映し、時代とともにその姿も変化してきました。
伝統的な素材漆喰と焼き物(やちむん)
古くからシーサー作りに用いられてきた代表的な素材は、漆喰(しっくい)と焼き物です。
漆喰(しっくい)シーサーは、砕いた赤瓦を骨組みに、漆喰で肉付けして色付けをします。
瓦職人が屋根の仕上げ材の余りで作ったのが始まりになります。その家の歴史を見守り続けるような素朴で温かい風貌が特徴になります。
焼き物(やちむん)シーサーは、沖縄の粘土を使い、釉薬をかけずに高温で焼く荒焼(あらやち)が一般的です。
屋根の上によく見られる赤茶色のシーサーはこのタイプになります。釉薬がないため雨風を吸い込み、年月を重ねるごとに独特の風合いが増していきます。
釉薬をかけて焼く上焼のシーサーは、色鮮やかで水や汚れに強く、室内に置かれることが多いです。
これらの伝統的な素材は、沖縄の風土に根ざした素朴さと力強さを持ち合わせており、かつての沖縄の家並みには欠かせない風景でした。
現代のシーサーに見られる変化と多様化
明治時代に庶民に広まった家獅子は、時代と共にその姿を大きく変え、多様化しています。現代では、観光客向けのお土産品やインテリアとして、様々な素材やデザインのシーサーが生まれています。
- 現代のシーサー:笑顔やコミカルな表情、デフォルメされた愛らしい姿が増加しています。
- 琉球ガラスや木工、レジンアートなど、素材や表現方法が多様化しています。
- 家を守る役割に加え、個性を楽しむ置物としての要素が強まる傾向もあります。
シーサーが「災いを防ぐ守り神」としてだけでなく、沖縄のシンボルとして広く愛されている証拠と言えるのではないでしょうか。
シーサーの正しい置き方と注意点
シーサーを自宅に迎える際、「正しい置き方」について気になる方も多いでしょう。シーサーを単なる置物ではなく、守り神としてその力を発揮してもらうためには、いくつかのポイントがあります。
基本的な設置場所と向き
シーサーの役割は、外からやってくる悪霊や災いを防ぐことです。そのため、基本的にシーサーの顔は、魔物が入ってくると考えられる方向、つまり外側に向けて置かれます。
沖縄では、魔物は人が通る道を歩くと信じられているため、人が通る方向へ向けるのが一般的です。
方角にこだわる場合は、鬼門とされる北東へ向けることで魔除けのご利益があるとされていますが、何よりも「家や家族を守る」という目的のために、外に向けることが大切です。
ペアで置く場合の「オス・メス」の区別と配置
対で置くシーサーには、一般的に口が開いているオスと口が閉じているメスがいるとされています。
オスの役割は邪気を祓う、福を呼び込む。
メスの役割は福を逃がさない、幸せを留める。
このオス・メスのペアで置く場合の基本的な配置は、シーサーを正面から見て、右側に口が開いたオス、左側に口が閉じたメスを置く「阿吽(あうん)」の形が主流です。
しかし、一体で置いても問題はなく、厳密なルールはありません。富盛の石彫大獅子も一体です。
沖縄旅行でシーサー作り体験ができる場所
沖縄本島には、シーサー作り体験ができる工房が数多く存在します。旅行の計画に合わせて、訪れやすい場所を選ぶのがおすすめです。
例えば、那覇市内や国際通り周辺には、アクセスしやすい体験工房があります。
観光地としても人気の高い「おきなわワールド」では、琉球ガラスや紅型染めなど、さまざまな沖縄文化の体験ができます。
その中にシーサー作り体験も含まれており、観光のついでに立ち寄るのに便利です。
また、沖縄本島中部にある「体験王国むら咲むら」も、多くの体験メニューを提供する複合施設です。こちらでも、プロの作家が丁寧に教えてくれるシーサー作りが人気を集めています。
沖縄の伝統的な街並みが再現されているので、シーサー作りの雰囲気も満喫できるでしょう。
その他、リゾートホテル内や、沖縄各地の道の駅、独立した小さな工房など、さまざまな場所でシーサー作り体験が可能です。
事前に予約が必要な工房もあるため、旅行の計画を立てる際に確認しておくのがおすすめです。
自分だけのオリジナルシーサーを作って、沖縄の旅をより一層思い出深いものにしてみてください。
まとめ

シーサーには、邪気を祓い福を呼び込むという沖縄の人々の切実な願いが込められています。伝統的な漆喰や焼き物(やちむん)の素材から、現代の多様なデザインまでその姿は様々です。
あとがき
沖縄の街を歩くと、本当にさまざまな表情や姿のシーサーに出会えます。それぞれに作った人の想いや願いが込められています。
自身の手で作るシーサーは、旅の素敵な思い出になるでしょう。

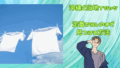

コメント