「最近、物忘れがひどくて…」そんな悩みを持つ若い世代が増えているようです。認知症は高齢者の病気と思われがちですが、実は30代や40代で発症する「若年性認知症」も増加傾向にあります。また、その前段階である「軽度認知障害(MCI)」も注目されています。自分や大切な人がもしそうだったら…と考えると不安になりますよね。本記事では、若い世代も知っておきたい認知障害の初期症状や予防法、そして周りの人ができることについて解説します。
認知症は高齢者だけの病気じゃない!
認知症と聞くと、多くの人が高齢者を思い浮かべるかもしれません。しかし、実は65歳未満で発症する「若年性認知症」が増加していることはご存知でしょうか。働き盛りの世代に起こるため、ご本人だけでなく、家族や周囲の人にも大きな影響を与えてしまいます。また、認知症の予備軍とも言われる「軽度認知障害(MCI)」も近年注目されています。
軽度認知障害は、日常生活に支障をきたすほどではないものの、記憶力や思考力に軽度の低下が見られる状態を指します。一方、若年性認知症は、仕事や生活に明らかな支障が出始める状態です。これらの初期段階で適切な対応をすることが、その後の生活の質を大きく左右する可能性があると言われています。
若い世代の認知症が増えている背景には、生活習慣病やストレスの増加、睡眠不足など、現代社会特有の要因が関わっていると考えられています。決して他人事ではない、身近な問題として捉えることが大切です。
若年性認知症と軽度認知障害の初期症状
「物忘れ」は誰にでも起こりますが、軽度認知障害や若年性認知症の兆候かもしれません。両者の違いを理解することで、早期発見につながる可能性があります。軽度認知障害の主な症状は、以下のようなものが挙げられます。
- 約束や大事な用事を忘れてしまうことが増える
- 物を置いた場所を思い出せない
- 新しいことを覚えるのが難しくなる
これらの症状は、ご本人も自覚できることが多いようです。一方、若年性認知症の場合は、物忘れだけでなく、以下のような症状がみられることがあります。
- 仕事の効率が明らかに落ちる
- 意欲がなくなり、趣味や好きなことに興味を失う
- 計画を立てたり、順序だてて物事を進めるのが困難になる
- 性格が変わったように感じる
「単なる疲労かな?」「ストレスかな?」と見過ごしがちですが、もしもこれらの症状が続くようであれば、専門家への相談を考えてみるのが良いかもしれません。
認知症になりやすいのはどんな人?
若年性認知症の発症には、様々な要因が関係していると考えられています。遺伝的要因だけでなく、以下のような生活習慣や環境も大きな影響を与えると言われています。
- 生活習慣病:糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、脳血管障害を引き起こし、認知症のリスクを高める可能性があります。
- ストレス:慢性的なストレスは、脳の機能を低下させることが指摘されています。
- 睡眠不足:十分な睡眠が取れない状態が続くと、脳内の老廃物が蓄積しやすくなり、認知症のリスクにつながると言われています。
- 運動不足:運動は脳の血流を良くし、神経細胞を活性化させるため、運動不足もリスク要因の一つと考えられます。
これらの要因は、現代社会を生きる多くの人に関わることかもしれません。日頃から健康的な生活を心がけることが、将来のリスクを減らす一歩となるのではないでしょうか。
今からできる!認知症の予防法
認知症を完全に予防することは難しいかもしれませんが、生活習慣を見直すことで、発症のリスクを減らすことができると言われています。以下の予防法を参考に、今日からできることを始めてみませんか。
- 脳を活性化する:読書や文章を書く、人と交流する、新しい趣味を始めるなど、脳に刺激を与える活動を積極的に取り入れましょう。
- バランスの良い食事:野菜や魚を積極的に摂取し、塩分や脂肪の多い食事を控えることで、生活習慣病の予防にもつながります。
- 適度な運動:ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、脳の血流を改善し、神経細胞のネットワークを保つのに役立つとされています。
- 質の良い睡眠:十分な睡眠をとることは、脳内の老廃物を除去し、記憶を定着させるために非常に重要です。
特別なことではなく、日々の小さな習慣の積み重ねが、将来の健康を守ることにつながるかもしれません。
家族や同僚としてできること
大切な人がもし、若年性認知症の症状に直面したら、どのように接すれば良いのでしょうか。まずは、早期発見と、ご本人への寄り添いが大切です。以下のような支援が考えられます。
- 専門家への相談を促す:「最近、どう?」などと優しく声をかけ、受診を勧めてみましょう。
- 日々の生活をサポートする:急な変化を求めるのではなく、ご本人のペースに合わせて、無理のない範囲でサポートをしましょう。
- 就労支援サービスの活用:若年性認知症の当事者には、仕事への意欲がある方も少なくありません。そのような場合、A型就労支援事業所などを活用することで、安定した就労を目指すことができます。
大切なのは、ご本人を責めることなく、その人の気持ちに寄り添うことです。温かく見守り、支える姿勢が、ご本人にとって大きな安心となるでしょう。
早期発見と正しい理解が未来を変える
若年性認知症は、早期に発見し、適切な治療や支援を開始することで、症状の進行を遅らせ、ご本人らしい生活を長く続けることができると言われています。一人で悩まず、以下のような専門機関に相談してみるのが良いかもしれません。
- 認知症疾患医療センター:専門医が在籍しており、正確な診断を受けることができます。
- 地域包括支援センター:地域の高齢者やその家族を支援する公的な機関です。
認知症は特別な病気ではなく、誰もがなり得る病気です。ご本人だけでなく、家族や社会全体で正しい知識を持ち、支え合うことが何よりも大切です。正しい理解と、温かい支えがあれば、きっと未来は変えられるのではないでしょうか。
まとめ
認知症は高齢者だけの病気ではなく、65歳未満で発症する若年性認知症が増加傾向にあります。その前段階である軽度認知障害(MCI)を含め、早期発見と適切な対応が非常に重要です。
物忘れだけでなく、仕事の効率低下や意欲の喪失など、見過ごされがちな初期症状を知ることが、予防や対策の第一歩となります。また、生活習慣病やストレス、睡眠不足など、発症には様々な要因が関係していると言われています。
日々の生活習慣を見直すことで予防につなげることができ、万が一の場合でも、家族や同僚の温かいサポートや、就労支援などの社会的なサービスを上手に活用することで、ご本人が自分らしく生きるための道を見つけることができます。
あとがき
今回の記事を作成するにあたり、若年性認知症について改めて深く考えるきっかけとなりました。働き盛りの世代に起こる認知症は、ご本人だけでなく、家族や周りの人にとっても計り知れない不安があると思います。だからこそ、正しい知識を持ち、適切なサポート体制を整えることが大切だと強く感じました。
認知症を「他人事」ではなく「自分事」として捉え、向き合うこと。そして、一人で抱え込まず、社会全体で支え合うこと。この記事が、そんな温かい社会を築くための一助になれば幸いです。

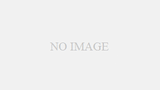
コメント